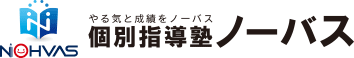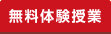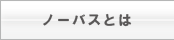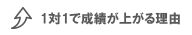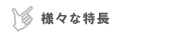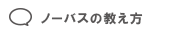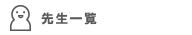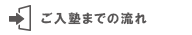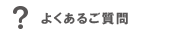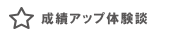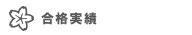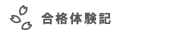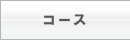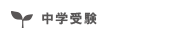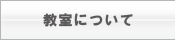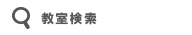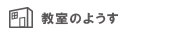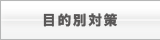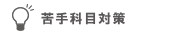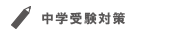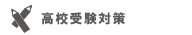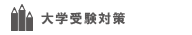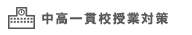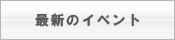お知らせ
共通テストまであと200日
こんにちは。
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
高校生は先週から今週にかけて1学期の期末テストがありますね。
今日も学校帰りに生徒が自習室に来て、頑張ってテスト勉強をしています。
高3生は1学期の成績次第で学校推薦が受けられるかどうかが決まります。
まだ志望校が定まっていない人も多いと思いますが、まずは目の前のテストに全力を注ぎましょう。
さて、令和8年度の共通テストまであと200日となりました。
これから共通テスト模試が増えてきて、その結果を踏まえて志望校を決めていくことになります。国公立大学を目指している生徒さんはもちろん、私立大志望の生徒さんも共通テスト形式の問題にしっかり慣れておきましょう。
ノーバスでは今日から夏期講習の個別授業がスタートしています。
「夏を制する者は受験を制す」というくらい大事な時期です。普段教わっていない教科でも講習は受けられますので、自分一人でやろうとせずに、どんどん活用しましょう!
個別指導塾ノーバス 宇都宮校
電話:028-649-8058
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
高校生は先週から今週にかけて1学期の期末テストがありますね。
今日も学校帰りに生徒が自習室に来て、頑張ってテスト勉強をしています。
高3生は1学期の成績次第で学校推薦が受けられるかどうかが決まります。
まだ志望校が定まっていない人も多いと思いますが、まずは目の前のテストに全力を注ぎましょう。
さて、令和8年度の共通テストまであと200日となりました。
これから共通テスト模試が増えてきて、その結果を踏まえて志望校を決めていくことになります。国公立大学を目指している生徒さんはもちろん、私立大志望の生徒さんも共通テスト形式の問題にしっかり慣れておきましょう。
ノーバスでは今日から夏期講習の個別授業がスタートしています。
「夏を制する者は受験を制す」というくらい大事な時期です。普段教わっていない教科でも講習は受けられますので、自分一人でやろうとせずに、どんどん活用しましょう!
個別指導塾ノーバス 宇都宮校
電話:028-649-8058
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
塾長日記 [2025-07-01]
自習室 空いています!
こんにちは。
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
今日から最高気温が30度を超える猛暑日が続きますが、皆さん体調管理はしっかり出来ていますか?
暑くて寝苦しい夜が続きますが、規則正しい生活を心掛けましょう。
さて効率よく勉強するためにも、勉強する環境はとても大切です。
特に夏場は暑さでやる気も体力も落ちやすく、お家にいるとついダラダラしてしまいがちです。勉強のスイッチを入れるためにも、ノーバスの自習室を活用してみてください。
ノーバスでは平日は15時〜22時、土曜日は14時〜21時で自習スペースを開放しています。
宇都宮校では自習室の隣に食事スペースを用意しているので、お弁当を持ってきて夜まで勉強を!というのも可能です。入退室のカードは忘れないようにお願いします。
自習室の利用についての質問がございましたら、教室までお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ】
個別指導塾ノーバス 宇都宮校
電話:028-649-8058(平日 15時〜22時、土曜日 14時〜21時)
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
担当:白井
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
今日から最高気温が30度を超える猛暑日が続きますが、皆さん体調管理はしっかり出来ていますか?
暑くて寝苦しい夜が続きますが、規則正しい生活を心掛けましょう。
さて効率よく勉強するためにも、勉強する環境はとても大切です。
特に夏場は暑さでやる気も体力も落ちやすく、お家にいるとついダラダラしてしまいがちです。勉強のスイッチを入れるためにも、ノーバスの自習室を活用してみてください。
ノーバスでは平日は15時〜22時、土曜日は14時〜21時で自習スペースを開放しています。
宇都宮校では自習室の隣に食事スペースを用意しているので、お弁当を持ってきて夜まで勉強を!というのも可能です。入退室のカードは忘れないようにお願いします。
自習室の利用についての質問がございましたら、教室までお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ】
個別指導塾ノーバス 宇都宮校
電話:028-649-8058(平日 15時〜22時、土曜日 14時〜21時)
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
担当:白井
塾長日記 [2025-06-26]
熱中症対策をしよう!
こんにちは。
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
蒸し暑い日が続きますが、皆さん体調管理は万全ですか?
炎天下の中の部活動で体調を崩す生徒さんが出てきています。何事にも全力で取り組むことが大事ですが、しっかり熱中症対策をしておきましょう。
具体的には
・水分をこまめにとる
・塩分も適度にとる(塩飴・経口補水液など)
・首元を冷やす(冷感タオルなど)・日傘を差す
・食事をしっかりとる・しっかり睡眠をとる
などです。
当たり前のことのように思えますが、油断禁物です!暑いと寝苦しかったり、食欲が落ちてしまいがちです。一度生活リズムが崩れるとなかなか戻らなくなりますし、免疫が落ちて病気にもかかりやすくなります。室内でも熱中症にかかるので、十分注意しましょう。
しっかり意識をして、自分の身体は自分で守りましょう。
暑くて家で勉強が出来ないという人は、是非ノーバスの自習室を活用してください。涼しくて快適に勉強できる環境が整っています。質問対応も受け付けているので、わからないところはどんどん聞きましょう。
ノーバスは皆さんの頑張りを応援しています!
個別指導塾ノーバス 宇都宮校
電話:028-649-8058(平日15時〜22時、土曜日14時〜21時受付)
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
蒸し暑い日が続きますが、皆さん体調管理は万全ですか?
炎天下の中の部活動で体調を崩す生徒さんが出てきています。何事にも全力で取り組むことが大事ですが、しっかり熱中症対策をしておきましょう。
具体的には
・水分をこまめにとる
・塩分も適度にとる(塩飴・経口補水液など)
・首元を冷やす(冷感タオルなど)・日傘を差す
・食事をしっかりとる・しっかり睡眠をとる
などです。
当たり前のことのように思えますが、油断禁物です!暑いと寝苦しかったり、食欲が落ちてしまいがちです。一度生活リズムが崩れるとなかなか戻らなくなりますし、免疫が落ちて病気にもかかりやすくなります。室内でも熱中症にかかるので、十分注意しましょう。
しっかり意識をして、自分の身体は自分で守りましょう。
暑くて家で勉強が出来ないという人は、是非ノーバスの自習室を活用してください。涼しくて快適に勉強できる環境が整っています。質問対応も受け付けているので、わからないところはどんどん聞きましょう。
ノーバスは皆さんの頑張りを応援しています!
個別指導塾ノーバス 宇都宮校
電話:028-649-8058(平日15時〜22時、土曜日14時〜21時受付)
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
塾生の皆様へ [2025-06-19]
期末テストで挽回しよう!
こんにちは。
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
高校生は先月の中間テストの結果が返ってきている頃ですが、結果はいかがでしたでしょうか?特に高校1年生は初めての高校のテストということで、対策が難しかったのではないでしょうか。
高校の成績はほぼほぼテストの点数によって決められています。
1学期の成績は1学期中間テストと1学期期末テストの点数の平均を取って出されますので、中間テストで成績が思わしくなかった人は、期末テストを頑張れば十分挽回ができます。結果に落ち込まずに、次のテストに向けてすぐに対策を講じましょう!
特に高校3年生は1学期までの成績で推薦が貰えるかどうかが決まってきます。出来ることを全てやってテストに臨みましょう!!
ノーバスでは、完全1対1の個別指導で各高校のテスト範囲や時期に応じた個別の対策をしております。コースやクラスによっても問題のレベルや範囲が変わりますので、学校での学習状況をしっかりヒアリングしたうえで生徒さんのレベルに合った指導をしております。
どの高校も6月下旬〜7月上旬で1学期の期末テストが行われます。
苦手な教科は今からしっかりと対策をして、成績アップを目指しましょう!!
勉強方法のご相談や無料体験授業も随時行っております。
ご希望の場合は教室に直接ご連絡いただくか、体験授業申込フォームよりお問い合わせください。
【お問い合わせ】
個別指導塾ノーバス 宇都宮校 担当:白井
電話:028-649-8058(平日 15時〜22時、土曜日 14時〜21時)
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
個別指導塾ノーバス 宇都宮校です。
高校生は先月の中間テストの結果が返ってきている頃ですが、結果はいかがでしたでしょうか?特に高校1年生は初めての高校のテストということで、対策が難しかったのではないでしょうか。
高校の成績はほぼほぼテストの点数によって決められています。
1学期の成績は1学期中間テストと1学期期末テストの点数の平均を取って出されますので、中間テストで成績が思わしくなかった人は、期末テストを頑張れば十分挽回ができます。結果に落ち込まずに、次のテストに向けてすぐに対策を講じましょう!
特に高校3年生は1学期までの成績で推薦が貰えるかどうかが決まってきます。出来ることを全てやってテストに臨みましょう!!
ノーバスでは、完全1対1の個別指導で各高校のテスト範囲や時期に応じた個別の対策をしております。コースやクラスによっても問題のレベルや範囲が変わりますので、学校での学習状況をしっかりヒアリングしたうえで生徒さんのレベルに合った指導をしております。
どの高校も6月下旬〜7月上旬で1学期の期末テストが行われます。
苦手な教科は今からしっかりと対策をして、成績アップを目指しましょう!!
勉強方法のご相談や無料体験授業も随時行っております。
ご希望の場合は教室に直接ご連絡いただくか、体験授業申込フォームよりお問い合わせください。
【お問い合わせ】
個別指導塾ノーバス 宇都宮校 担当:白井
電話:028-649-8058(平日 15時〜22時、土曜日 14時〜21時)
メール:utsunomiya@nohvas-juku.com
塾長日記 [2025-06-10]













 お知らせ全て
お知らせ全て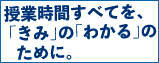


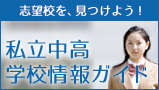

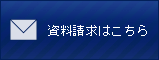
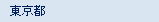
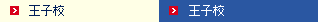
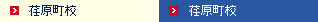
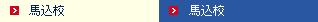
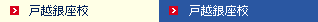
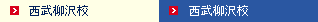
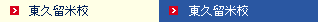
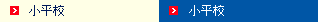
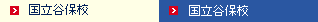
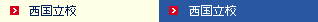
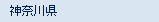
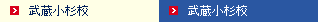
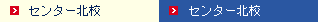
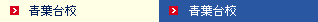
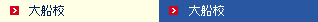
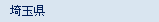
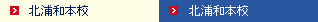
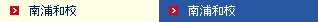
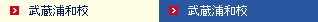
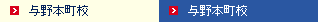
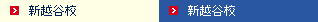
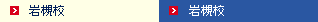
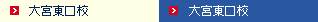
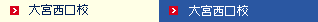
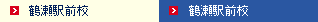
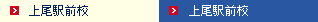
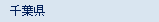
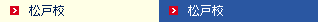
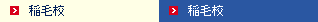
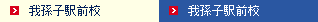
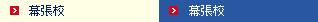
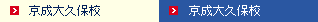
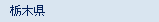
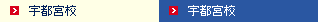
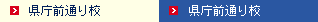
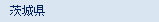
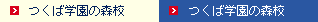
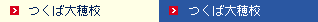
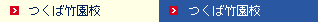
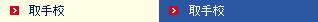
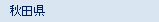
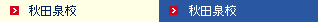
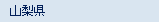
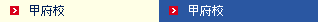
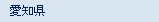
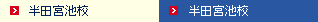
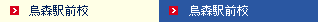
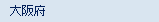
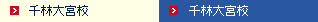
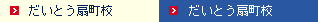
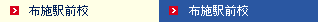
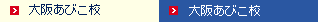
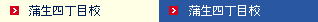
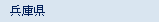
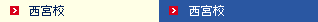
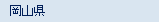
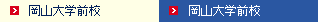
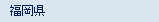
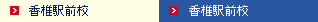
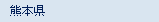
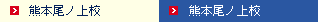

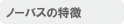

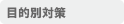




 2025-06-03
2025-06-03 2025-03-06
2025-03-06 2025-02-28
2025-02-28 2024-09-02
2024-09-02 2024-03-08
2024-03-08 2023-09-11
2023-09-11 2023-09-05
2023-09-05 2023-08-07
2023-08-07 2022-12-08
2022-12-08 2022-09-27
2022-09-27 2022-09-01
2022-09-01 2022-06-17
2022-06-17 2022-06-17
2022-06-17 2022-05-16
2022-05-16 2022-05-09
2022-05-09 2022-02-25
2022-02-25 2021-11-19
2021-11-19 2021-09-01
2021-09-01 2021-05-06
2021-05-06 2025-07-02 だいとう扇町校
2025-07-02 だいとう扇町校 2025-07-01 東久留米校
2025-07-01 東久留米校 2025-07-01 小平校
2025-07-01 小平校 2025-07-01 香椎駅前校
2025-07-01 香椎駅前校 2025-07-01 西国立校
2025-07-01 西国立校 2025-07-01 西武柳沢校
2025-07-01 西武柳沢校 2025-07-01 大宮東口校
2025-07-01 大宮東口校 2025-07-01 熊本尾ノ上校
2025-07-01 熊本尾ノ上校 2025-07-01 宇都宮校
2025-07-01 宇都宮校 2025-07-01 塾本部
2025-07-01 塾本部